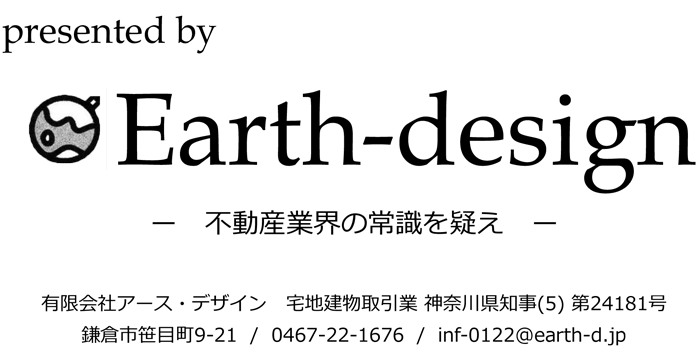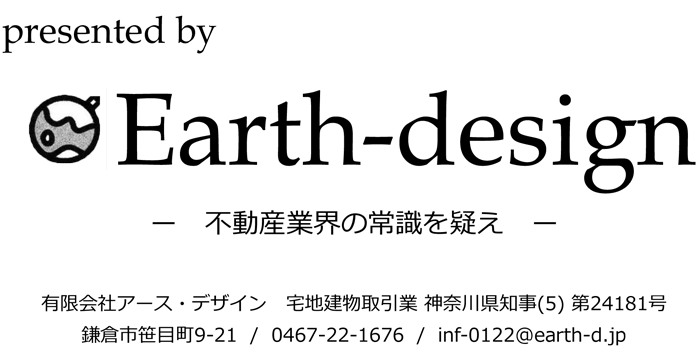目次
部分的補強
住宅を設計する際、ピアノや書棚の重量物は熟考しないと、後から大変なことになる。これは多くの方が経験上ご存じのことでしょう。
しかし長い生活の中で、そうも言っていられない事情が生じる場合があると言うことも、多くの方がご存じのことでしょう。
子供の成長や独立にあわせて、大がかりな間取りの変更や重量物の移動に関しても、木造建築は非常に自由度が高いです。



まず、根太をよけて、古い床材を適切な長さでカットしてゆきます。壊して撤去の方が勿論、速いのですが、なぜこんなに手間の掛かることをやっているかと言えば、施主のリクエストが、この古材を再利用する…「建物の風合いを損ないたくない」であり、この床材、なんと後で使います。
写真を見ていただくと、古い根太の取り付け後が新鮮に見えますね。この間隔を狭めてゆくことで根太の本数を増やして、重量物に対応できる床にしてゆきます。
勾配床の解消と風合いの継承



この床には実は大きな特徴があり、左写真の奥と手前の、異なる床高さの建物の接合部でした。床高さの異なる建物を繋ぐため、この建物では「勾配床」という手法が選択されていたのですが、昭和の初め頃まではもしかするとオシャレだったのかも知れませんが、使いやすさを考えれば段差を出してしまった方が無難です。
あえて一段、段差を付けて、その部分を台所の間仕切りとして区分します。
厳重に水平を出し、ピッチを詰めた根太が並べられます。
仕上がりの床には、いかにも「リフォームをやりました」という安っぽさや味気なさも無く、古いながらも美しい清潔感があり、しかし構造的にはピアノも置けるという、すばらしい仕上がりになりました。
写真奥に見えているのが「引き込み」という半屋外の機能であり、右側に見えているのは普通の床面を大胆にくりぬいて風呂場を作っているところです。
旧来、このなんでもない広いリビングという機能だった場所を、「重量物対応の書庫」「台所」「書斎」「脱衣所」「風呂場」という機能に変更しています。それらの経緯はまた別な記事に書きたいと思います。
大がかりな間取りや機能の変更に対して、木造建築は他の構造よりも非常に自由度が高いです。