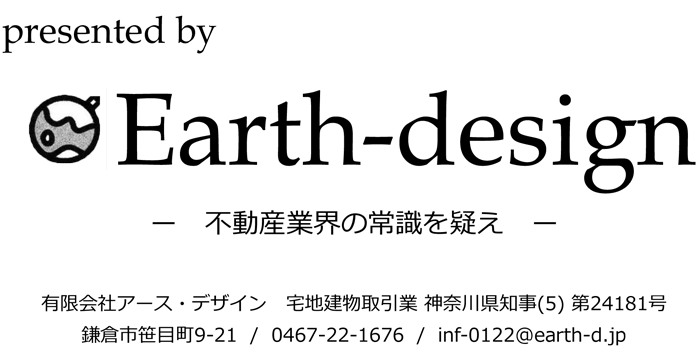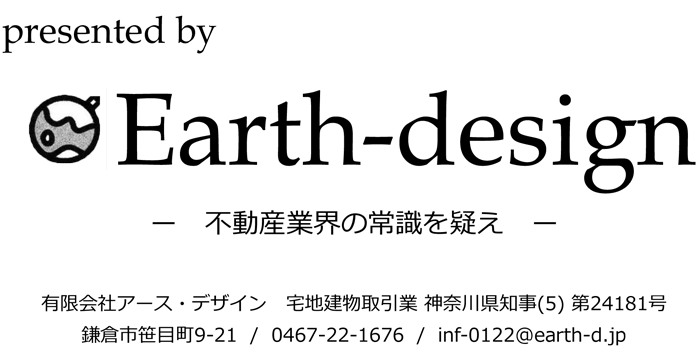目次
疑問!
疑問があります。
その取引は、買主にとってお買い得だったのか?
そうではなくて、売主が高額に売りつけただけなのか?
大きな問題として一つ言えることがあるとすれば、ほとんどの不動産業者が、こうした優劣の曖昧な取引を自ら誘導しておきながら、自身の立場を不明瞭にしたままに、「売主と買主」の双方との付き合いを思考することで、自身の利益だけは二倍に伸ばすという営業スタイルを保持しているという現実なのでは無いでしょうか。
不動産の価格(評価)に対する誤解
最初に答えから書きますが、売買における不動産の価格を数学的に求めようと考えるのは誤りです。ここが納税のために求める不動産の評価と大きく異なる部分です。
以下、チャートをご覧いただければ一目瞭然なのですが、売買における不動産の価格は、一坪という単価当たりで実例を統計化した場合、「○市○町○丁目」という、同一丁内の極めて狭いエリアにおいても、全く類似分布などせず、むしろバラバラになる事がほとんどなのです。

例えばオレンジ色の四角形が同一丁内の過去20年の間の実際の取引単価なのですが、坪150万~300万くらいまでの分布となり、一例として30坪の土地を想定しても、その売出価格は4,500万~9,000万というとんでもない開きになります。これが普通のことなのです。
乱暴に聞こえるかも知れませんが、現実の売買取引の「解答」がこの分布である以上、その30坪の土地は4,000万で売ってしまっては失敗で、1億で買ったら失敗であると言うことくらいしか、明確に言い切れることは無いと言うことになるのではないでしょうか。
当社の立ち位置
まとめ
今の不動産業界では非常に珍しいことなのかも知れませんが、創業以来、当社では全職員含めて、「今、自分が守るべき対象が誰なのか」「誰のために働いているのか」を明確にすることを絶対事項としています。このため当社と「購入コンサル契約」を締結されているお客様に対しては、折々に、事前に、以下の注意喚起をしております。
(1)当社が双方代理をする場合
そこに買主Bさんから当社に仲介の依頼(購入申し込みや具体的な相談)がありました。この場合、Bさんも当然に当社の顧客となります。当社はAさんだけではなく、Bさんの利益にも配慮をしながら仕事をしなければならない立場となります。よって、当社が8,500万を目指して取引をまとめると言うことは出来ません。
しかし一方でAさんの損害も当社は絶対に出せない立場ですから、概ねの中値、7,000万以下の取引をAさんに提案することもあり得ません。あくまでもBさんに利益のあるであろう範囲の価格設定で、例えば500万~1,000万値引きの8,000万~7,500万等の価格を想定し、Bさんに他の選択肢があることも提示をしつつ、まずはBさんの合意を得ます。
ここでBさんがこの物件に拘らず、弊社に別途購入コンサルの依頼等をされ、他の物件も探すというのであれば、当社がBさんに提示する目標値は、あくまでも○市○町○丁目のエリアであればその底値。坪150万~200万。30坪なら4,500万~6,000万の土地と言うことになります。
では仮に8,200万でもBさんがこの物件を購入したいと考えた場合はどうするのか。これは当社が2000年の創業以来、一貫して全ての購入コンサルの顧客にしてきた対応の通り、まずは「反対」をし、それでもBさんに同意をいただけない場合には更に反対の理由をしつこく明確化し、それを全て承知でBさんが購入されると言うことであれば、取引に係るBさんのリスクを全て排除しつつ(勿論Aさんも)、そこではじめて取引を進めていきます。
お読みいただくのが恐縮してしまうほど、ややこしい仕組みになっていると思います。
でも再度お伝えしたいのは、本来はこのくらい思い悩んだり、考えることが山ほどある双方代理取引を、自社の利益が二倍になるという理由だけで、ほとんどの不動産業者がなんとなく実施しているという現実です。
これは消費者の利益保全という観点からは、非常に大きな不動産業界の問題であろうと思います。
あえてもう一言加筆しますが、「双方代理」がダメなのでは無いと思います。「双方代理」の場合に、各々の利害のぶつかる立場にある売主、買主が、各々のメリットとデメリットや可能性について、一切、説明をされていない現状が問題であるとの指摘をしています。
プロの不動産業者であれば、当社がここに記載しているような仕組みになっていることは、百も承知なのですから。全て承知で少し高いけれど良い物件だから買うという判断も、事情があるから少し安いとは思うが、今、この取引をまとめることが優先だから売るという判断は、いくらでもあり得る、健全なものでしょう。
(2)当社が双方代理をせず、他の不動産業者Dが買主Cさんを紹介する場合
当社の立場を明確にと言うお話でした。このパターンは非常に分かりやすく、Cさんは当社の顧客ではなく(共同仲介なので、法的な詳細解釈はそうはならないのですが、あくまでも考え方として)、Aさんが当社の顧客ですから、当社はAさんの利益のみを追求します。
Cさんの利益はCさんの代理人たる不動産業者Dが保護すれば良いという考え方です(するかしないかは弊社には関わりすらないことです)。よって当社が目指す成約価格はあくまでも8,500万円。許容できる交渉範囲はせいぜい50万~100万前後が良いところとなるでしょう。勿論、このタイミングでAさん自身に売り急がなければならない事情が生じたり、Aさん自身の指示で価格を落としても話をまとめよとのご指示があれば、当社がそれに従って業務する事は言うまでもありません。
(3)買主様向け(1)(2)総括
簡単に書いてしまえば、そもそも当社が売主のコンサルをしている物件は売主の利益を損なってまでの、格安な取引は出来ないということになります。
格安でなくとも、非常に良い物件だから、妥当な金額であれば購入したいという場合には、当社に対して是非、直接の価格交渉をお申し出下さい。当社は買主にとってのメリットのある価格を目指し、買主との十分な協議を経て、売主にソコまでの折り合いに同意をいただけるのかという交渉を致します。
当社の売物件は買わないように
どうしても購入を検討する場合には、十分に適正な減額交渉を行うように
本来、不動産業者が売主から売却の仲介依頼を受けている物件を買主に紹介する場合、上記の注意喚起がなければ、取引の構造として根本的にどこかがおかしいでしょう。
しかし、こうした注意喚起を不動産業者から受けたことのある消費者は皆無であると思います。
不動産に「同一物は存在しません」から、どうしてもその物件が良ければ、売主にもある程度利益のある、まさに適正価格の取引を買主が受け入れるしかありません。しかし「似たような物」は、「二度と無い」などと言うことは全くなくて、実はいくらでも、時間さえ掛ければ出てきます。
購入コンサルの場面において、当社が目指すのは買主の利益の追求ですから、自社物件であろうと、当社業務報酬が二倍になろうと、買主の利益にならない取引には反対をします。売主、買主、各々の利益の先にしか、当社の報酬は発生しないというのが、当社の根本思想だからです。